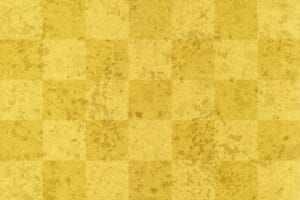コーダ(CODA)とは?聴覚障害の親を持つ子どもたちに必要な支援

最近「コーダ(CODA)」という言葉を初めて知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。これまで私たちは、どちらかと言えば障がいを持つ本人への支援に目を向けることが多かったかもしれません。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
しかし実際には、その家族や周囲の人々もまた特別な役割を担い、ときに大きな負担や悩みを抱えています。
本記事では、聴覚障害の親を持つ子どもを意味するコーダについて、直面する課題や現在の社会支援状況をまとめました。
これをきっかけに家族と社会、そして私たち一人ひとりがどのように関わることができるのかを一緒に考えてみましょう。
コーダ(CODA)とは
CODAとは「Children of Deaf Adults」の略語で、日本語では「ろう者や難聴の親を持つ、耳が聞こえる子ども」を意味します。
1983年にアメリカで生まれた言葉で、日本では1994年に講演を通じて「コーダ」という言葉と意味が紹介されたのが初めてとされています。
親が両耳とも聞こえない場合はもちろん、片方の親が聴覚障害を持つ場合や、日常的に手話を使う家庭でも、そこで育つ聞こえる子どもはすべて「コーダ」とされています。
つまり、コーダは「耳が聞こえるけれども、ろう者の文化の中で育つ子ども」という立場を持つのです。
コーダの特徴と文化的背景
コーダは「耳が聞こえる」という点では聴者と同じですが、育つ環境は大きく異なります。
親が手話を使ったり、視覚的に情報をやり取りする文化の中で生活してきたため、独自の特徴や感覚を自然に身につけるのです。
この背景を理解することは、コーダを知る第一歩でもあります。
ろう者の家庭では、耳からの音ではなく目を通じた情報が生活の中心になります。
そのため、コーダも幼い頃から「目で見て理解する習慣」を身につけます。
例えば、会話をするときは必ず相手の目を見て話すことが自然になりますし、表情やジェスチャーを大きく使うことで感情を伝える力も育まれます。
こうした環境は、聴者の世界で育った子どもにはなかなか得られない体験です。
学校や社会に出たときに「表現が豊か」「相手の感情を読み取るのが上手い」と感じられることも少なくありません。
コーダの持つ特徴は、家庭の文化そのものから生まれていると言えるでしょう。
実は知られていないコミュニケーションの実態
コーダの家庭での会話方法は実は一様ではなく、多様性に満ちています。
ある調査によると、手話だけで親と会話する人はおよそ14%に過ぎません。最も多いのは、手話に加えて口話や身振り、さらには筆談を組み合わせてコミュニケーションをとる形で、全体の約46%を占めていると言われています[1]。
また、会話について「問題なくできる」と答えた人もいれば、「だいたい理解できる」という回答もほぼ同じ割合でした。
つまり、すべてのコーダが手話を完璧に使えるわけではないのです。
家族の聞こえ方やコミュニケーションスタイルによって、子どもが身につける手段も変わります。
この点は「コーダはみんな手話が得意」という誤解を解く重要な視点です。
多様な形で親とやり取りをしてきた経験が、コーダを独自の存在にしているとも言えるかもしれません。
コーダの認知が広まった映画『CODA あいのうた』
「コーダ」という言葉を一気に広めたきっかけのひとつが、2021年に公開され、アカデミー賞で作品賞を含む主要3部門を受賞した映画『CODA あいのうた』です[2]。
物語は、ろう者の両親と兄のもとに生まれたひとりの少女が主人公です。
唯一聞こえる存在である彼女は、家族の通訳を担いながら成長し、自分の夢と家族の期待との間で葛藤します。
映画を通じて、初めて「コーダ」という立場を知った方も多く、障がい者本人ではなく、その家族が背負う現実を描いた点が、多くの共感を呼んだのです。
この作品は、日本においても「コーダの存在を理解する入り口」となり、社会的な認知を大きく押し上げました。
日本国内にも2万2,000人いるコーダ
日本国内には、現在およそ2万2,000人のコーダがいると推定されています。
決して少ない数字ではないものの、その存在が社会に広く知られるようになったのはごく最近のことです。
これまでは「親が耳の聞こえない子どもは特別な存在」という認識が強く、当事者自身の声が社会に届く機会は限られていました。
しかし調査や実態報告が重ねられるにつれ、幼い頃から家族の通訳を担ったり、聴者とろう者の世界をつなぐ役割を果たしたりと、コーダが果たしている大切な役割が見えてきました。
さらには、コーダ自身が持つ悩みも深く、こうした背景から教育や福祉の分野では「コーダをどう支えるか」が課題として取り上げられるようになっています。
コーダが抱える悩みと社会的課題
コーダは、成長の過程で障がい者の親や兄弟に大きな力を得る一方で、独自の悩みや負担を背負うことも少なくありません。
社会からは「聞こえる子ども」として見られがちですが、家庭内では特別な役割を担うことが多く、時には子どもらしさを犠牲にせざるを得ない状況に直面します。
幼少期からの通訳負担
多くのコーダが最初に直面するのは、幼い頃から通訳を担うという現実です。
ある調査によれば、平均すると6歳前後から親の通訳を始めており、その頻度は週に4日以上にのぼるとされています[2]。
買い物や来客対応といった日常的な場面だけでなく、病院での診察や銀行での手続きなど、大人でも難しい内容を任されることもあります。
本来なら子どもが担うべきでない責任を早い段階で負うことは、精神的な負担につながりやすいと言われています。
それでも多くのコーダは、家族の役に立ちたいという思いから、無理をしてでも対応してきました。その積み重ねが大きな成長につながる一方で、心の中には疲れや葛藤を抱えているのです。
ヤングケアラーとしての側面
近年、社会的に注目されている「ヤングケアラー」という言葉があります。
これは、子どもや若者が家族の介護や生活支援を担う状況を指すものです。
コーダの中には、幼い頃から通訳や家庭の手助けを担ってきた結果、ヤングケアラーに該当すると考えられる人もいます。
もちろんすべてのコーダがヤングケアラーというわけではありません。
しかし、過度な通訳負担や心理的な責任を抱えてきた人については、適切な理解と支援が必要です。
この視点が広がることで、コーダの悩みが個人の問題ではなく、社会全体で共有すべき課題であることが見えてきます。
コーダへの理解と支援の現状
日本では、少しずつコーダへの支援が進められています。その中心のひとつが「J-CODA」という当事者組織です[3]。
ここでは、同じ立場の人同士が体験や思いを語り合い、勉強会やセミナーを通して理解を深める取り組みが行われています。
孤立しやすいコーダにとって、このような場は安心できる居場所となっています。
その一方で、国内に2万人以上いる現実から考えると、コーダの存在がまだ十分に知られていることは社会として無視できない規模であり、一層の理解を広げ、支援の手を差し伸べることが重要になっています。
障がい者とその家族に対して私たちができる支援の力
コーダの存在を知ることは、障がい者本人への理解を深めるだけでなく、「その方を支える家族にも課題がある」という事実に気づかせてくれます。
家族の中で唯一耳が聞こえる子どもが担う役割は、時に大人顔負けの責任を含むものであり、その負担を軽減するには社会全体の協力が欠かせません。
障がい者支援というと、本人に直接手を差し伸べることばかりに意識が向きがちです。
しかし、支える家族や周囲の人々にも寄り添う姿勢がなければ、本当の意味での支援は成り立ちません。コーダの実態は、そのことを私たちに強く示しています。
では、こうした障がい者支援、そしてその方を支える家族に対して、私たちができることは何でしょうか。
身近なことに目を向けてみると、日常の中で少し意識を変えるだけでも支援につながります。
- 耳の聞こえない方と話すときに筆談やスマートフォンの文字入力を使う
- 公共の場で手話通訳を見かけたら安心して利用できるよう温かく見守る
- 当事者やその家族の声に耳を傾ける
このような小さな行動1つとっても、障がい者の方、ならびに家族の負担を和らげる大きな力となります。
また、障がい者の社会的活動を支えるNPO団体も数多くあり、こうしたNPOの活動を支援することも、私たちにできる支援の在り方の1つとなります。
お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことができます。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。
あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問い合わせください。
<参考文献>
[1]中津真美:東京大学バリアフリー支援室特任助教,「コーダという子どもたちのこと:きこえない親をもつきこえる子ども」,available at https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/nb804c8a16b3b?utm_source=chatgpt.com
[2]映画『Coda コーダ あいのうた』公式サイト,available at https://gaga.ne.jp/coda/
[3]J-CODA,available at https://jcoda.jimdofree.com/
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND