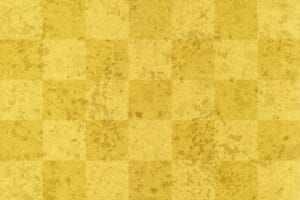ステレオタイプとは?無意識の思い込みで差別や偏見を生まないために

最近、「ステレオタイプ」という言葉をテレビや新聞、インターネットで見聞きすることが増えてきたと感じる方も多いのではないでしょうか。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
社会問題や差別、ジェンダーといった話題とともに取り上げられることも多く、その背景には、現代社会がますます多様化していることが関係しているようです。
ステレオタイプとは一体どういう意味なのか、日本社会の中ではどんな形で存在しているのか、そしてこうした問題に対して、自分にも何かできることがあるのだろうかと、関心を持たれているかもしれません。
そこで本記事では、ステレオタイプの基本的な意味から身近な具体例、さらには社会に与える影響や私たち個人にできる向き合い方までを、詳しく解説していきます。
今こそ、知識として知るだけでなく、暮らしの中で意識し、行動に生かしていくための一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
ステレオタイプとはどんな意味?
ステレオタイプとは、ある集団やカテゴリーに属する人々に対して、一律のイメージや性質を当てはめてしまう思考を指す言葉です。
たとえば、「女性は感情的である」とか「高齢者は保守的で変化を嫌う」といったように、個々人の違いではなく、集団全体に同じ特徴があるかのように捉えてしまう傾向のことです。
こうした考え方は、私たちが複雑な社会の情報を整理したり、効率的に理解したりするために働く一種の認知的な仕組みから生まれるものです。
そのため、誰もが無意識のうちに何らかのステレオタイプを持っていることがほとんどです。
しかし、ステレオタイプはときに個人の尊厳を傷つけたり、偏見や差別を助長したりするリスクもあります。
とりわけ、社会の中で少数派にあたる人々に対して使われた場合には、大きな不利益を与えることさえあるのです。
ここでは、ステレオタイプという言葉の意味を正しく理解したうえで、私たちの身の回りにどのような形で存在しているのか、また、それが社会や個人にどのような影響を与えているのかを、順を追って見ていきましょう。
ステレオタイプと固定観念の違い
「ステレオタイプ」という言葉に似た表現に、「固定観念」というものがあります。
どちらも“思い込み”という意味で使われることがありますが、実は微妙に意味合いが異なっています。
固定観念とは、ある事柄に対して個人が強く信じ込んでいる思考パターンのことを指します。
たとえば「男は外で働き、女は家を守るべきだ」といった考え方は、時代が変わっても一定層の個人の考えとして根強く残っている固定観念の一例です。
これは個人の価値観として内面化されている場合が多く、必ずしも他人に押しつけるものではないケースもあります。
一方、ステレオタイプは個人の信念というより、社会的に共有されたイメージであることが多いのが特徴です。
つまり、ある程度の人数が「そうだろう」と思い込んでいる集団的な認識が、ステレオタイプの核となっているのです。
このように、固定観念は「個人に根差す思い込み」、ステレオタイプは「社会的に共有された思い込み」というように使い分けると、理解しやすいかもしれません。
ステレオタイプとバイアスとの違い
「バイアス」という言葉も、ステレオタイプと並んでよく使われる関連用語のひとつです。
バイアス(bias)は、特定の方向に思考が偏ってしまう心理的な傾向のことです。
ステレオタイプは、こうしたバイアスの一種として分類されることが多く、特に「集団に対する一律のイメージ」に基づいた偏りを意味します。
そのため、「ステレオタイプ=バイアスの中のひとつ」と捉えると位置づけがはっきりするのではないでしょうか。
つまり、バイアスはより広い概念であり、ステレオタイプはその中でも、社会的カテゴリーに属する人々に対して抱く画一的な見方に特化したものと考えられます[1]。
日本にも見られるステレオタイプの身近な例
ステレオタイプというと、まだ日本人には馴染みのある言葉ではないため、海外の話や特定の社会問題だけを連想されがちですが、実際には日本社会の中にもさまざまな形で根づいています。
気づかないうちに口にしてしまう言葉や、日常の中で当たり前のように共有されているイメージの中にも、ステレオタイプは数多く存在しています。
特に問題となるのは、それらが無意識のうちに人の評価や行動に影響を与えたり、不利益を生むきっかけになっている場合です。
では、私たちの身近なところには、どのようなステレオタイプがあるのでしょうか。いくつかの具体的な例を見ていきましょう。
ジェンダーに関すること
SDGsの取り組みが広く知られるようになって、社会的・文化的な性を指すジェンダーに基づく関心は日本でも広がっています。
こうしたジェンダーに対するステレオタイプは、現在でも根強く残っています。
たとえば、「女性は感情的で人付き合いが得意」「男性は冷静で論理的に判断する」といったイメージがその代表です。
こうした考え方は、家庭や職場、教育現場などさまざまな場面で影響を及ぼしてきました。
女性がリーダーシップをとることに違和感を持たれたり、男性が感情を表現することを「男らしくない」と捉えられたりするのも、こうしたステレオタイプの影響と言えます。
また、子どもに対する接し方にも違いが見られることがあります。
女の子には「優しく」、男の子には「強く」といった言葉がかけられる場面も未だあるかもしれません。
このように、無意識のうちに性別による役割を押しつけてしまっていることが少なくないのです。
地域性や県民性の特徴
「関西人はお笑い好き」「東北の人は無口で真面目」「東京の人は冷たい」など、日本各地の地域性や県民性にまつわるイメージも、ステレオタイプの一種です。
こうした県民性は、テレビ番組や雑誌、ネット記事などでもよく取り上げられる話題で、親しみやすいものとして定着している傾向があります。
もちろん、地域による文化や方言の違いは存在しますが、そこに一律の性格や価値観を結びつけてしまうと、個人を正しく理解することが難しくなります。
たとえば、関西出身の人が「もっと面白いこと言ってよ」と求められたり、東北出身の人が無口でない場合に「意外」と言われたりするのは、まさにステレオタイプによる誤解の表れと言えるのではないでしょうか。
このような地域的な思い込みは、気軽な話題として使われることも多いですが、繰り返されるうちに偏見やラベリングにつながることもありますので、注意が必要です。
血液型による性格・行動
日本では、血液型と性格や行動を結びつける文化が長年根強く存在しています。
「A型は几帳面」
「O型はおおらか」
「B型はマイペース」
「AB型は変わり者」
いずれかの血液型の方は、こうした印象を持たれた経験がある方も少なくないのではないでしょうか。
このような血液型性格診断は、エンタメや占いの一環として楽しまれることも多いですが、職場や人間関係の中でときとして「本気の評価」として扱われてしまうと、重大な誤解や偏見につながることもあります。
血液型と性格に明確な相関関係があるという科学的根拠はないにもかかわらず、就職の面接や学校生活で「この人はB型だから自己中心的なのでは」といったレッテルが貼られることがあれば、それはまさにステレオタイプによる弊害となります。
相手の人間性を知る前に、表面的な属性で性格や行動を決めつけてしまう。このような思考パターンが、社会的な誤解を生む原因にもつながっています。
ステレオタイプが引き起こす社会的影響とは
このようにステレオタイプは、日常的な会話の中で無意識に扱われがちな側面もありますが、それらが社会全体の共通認識となった場合には、深刻な影響を及ぼすことがあります。
特に、そのステレオタイプが差別や偏見と結びついたときには、機会の不平等や社会的な分断を引き起こす要因にもなりかねません。
ここでは具体的にステレオタイプが社会にどのような影響を及ぼすのか、個人レベルから集団レベルまで3つの視点で掘り下げていきます。
ステレオタイプと差別・偏見の関係
ステレオタイプが社会問題として注目される最大の理由は、それが差別や偏見の温床になり得るからです。
たとえば、「高齢者は新しい技術に疎い」といった一般化された見方が職場に広がってしまうと、年齢を理由に重要な仕事を任されなかったり、採用の段階で選考対象から外されてしまったりすることもあるのです。
このように、特定の属性に基づいて個人を評価・判断することは、「年齢差別」「性差別」「人種差別」などと結びつく恐れがあります。
表面上は単なる“印象”や“思い込み”であっても、社会構造の中に取り込まれてしまえば、それはれっきとした差別のメカニズムとなってしまいます。
また、メディアや教育現場、昨今ではSNSの普及によって、特定のイメージを繰り返し提示されることにより、無意識のうちに偏った価値観が定着することがあります。
知らず知らずのうちに、他者を不公平に扱う判断を下している可能性があるのです。
個人の可能性を制限する「ステレオタイプ脅威」
ステレオタイプがもたらす影響は、社会構造だけにとどまりません。
個人の心の中にまで深く入り込み、その人自身の行動や成果に影響を与えることも知られています。
特に注目されているのが、「ステレオタイプ脅威」と呼ばれる心理現象です[2]。
これは、自分が属する集団に対してネガティブなステレオタイプが存在すると、その評価を気にするあまり、自分本来の能力やパフォーマンスを発揮できなくなってしまうというものです。
たとえば、「女性は数学が苦手」という固定観念の中で育った女の子が、数学の試験を受けるときにそのイメージを意識することで、本来の力を出せなくなることがあります。
これは単なる緊張とは異なり、社会的なイメージが自分自身の行動にまで影響を及ぼしている状態です。
このような現象は、性別だけでなく、人種や年齢、出身地、さらには学歴など、あらゆる属性に対して起こり得ます。
つまり、ステレオタイプは「見る側の誤解」だけでなく、「見られる側の自己抑制」まで引き起こしてしまうことがあるのです。
社会全体への悪影響
最後に、ステレオタイプが社会全体にもたらす影響について考えてみましょう。
ステレオタイプは、異なる価値観や背景を持つ人々のあいだに壁を作り、共感や理解を妨げる要因になりがちです。
私たちは多様な個人が共存する社会に生きていますが、ステレオタイプによって「この人はこういう人に違いない」と決めつけてしまうと、本来築けるはずだった関係性や協力の可能性が失われてしまいます。
これは、職場のチームワークや地域社会の連携、さらには国際的な交流の中でも大きな障害になりかねません。
また、ステレオタイプが前提となった制度や方針が作られてしまうと、個人の多様性が無視された政策が実行される危険性も出てきます。
たとえば、子育て支援の制度設計において「母親が担うべき」といった前提が組み込まれていれば、父親や多様な家族形態への配慮が不足することになります。
こうした現象は、結果として社会の持つ包摂性(インクルーシブ性)を弱め、分断や対立を深める引き金になることもあるのです。
誰もが持つステレオタイプと共存できる社会へするために
ここまで見てきたように、ステレオタイプは私たちの身近なところに存在し、知らず知らずのうちに他者との関係や社会全体の構造に大きな影響を及ぼしています。
しかし、こうした思考のクセは、私たちの脳が情報を処理する際の“効率化”のために備えている、ある意味で自然な機能でもあるため、ステレオタイプそのものを完全になくすことはできません。
それでは、私たちはこの問題にどう向き合っていけばよいのでしょうか。
1つには「ステレオタイプを持っていること自体を否定するのではなく、それに気づき、向き合う姿勢を持つこと」だといえるでしょう。
そしてもう1つ重要なのは、情報との付き合い方です。
特に現在はSNS等により、個人の発信が大多数集まることで社会的なイメージを作り上げてしまうことも少なくありません。
私たちにできるのは、そうした情報を鵜呑みにせず、複数の視点から物事を見る批判的思考を養うことも、ステレオタイプに流されないための土台になると言えます。
もちろん、こうした取り組みは一朝一夕で効果が出るものではありません。けれども、一人ひとりが少しずつ意識を変えることが、結果的には社会全体の空気を変えていく力になります。
多様性を尊重し、個々の違いを大切にできる社会の実現のために、まずは「ステレオタイプとは何か」を知ることから始め、日々の暮らしの中で小さな実践を重ねていくことが、私たち一人ひとりにできる大きな一歩なのではないでしょうか。
お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
(KOBIT編集部:Fumi.T)
<参考文献>
[1] 池田まさみ・森津太子・高比良美詠子・宮本康司 (2020). 利用可能性ヒューリスティック 錯思コレクション100,available at https://www.jumonji-u.ac.jp/sscs/ikeda/cognitive_bias/cate_s/s_22.html
[2]日経サイエンス,「ステレオタイプ脅威」,available at https://www.nikkei-science.com/201405_038.html
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND