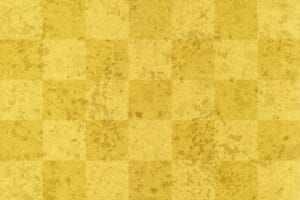ドヤ街とは?歴史背景から考える日本の住み続けられるまちづくり

昭和の日本を歩んできた方にとっては「ドヤ街」と聞くと、どこか物悲しく、少し近寄りがたい印象を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。逆に言葉そのものを初めて聞いた方には、賑やかな街並みを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
「ドヤ街」という言葉の背景には、日本の高度経済成長を支えた「人々の暮らし」が深く関わってきました。本記事では「ドヤ街とは?」をテーマに、日本の社会課題とこれからを考えていきたいと思います。
ドヤ街とは?意味や由来を歴史背景から紐解く
ドヤ街とは、経済成長著しい戦後の日本において、都市部に点在する簡易宿泊所が密集している地域を指す言葉として使われ始めました。
主に日雇い労働者や低所得の方々が集まり、安価な住まいを求めて暮らしてきた場所として知られています。
衛生上の問題や強盗などの事件も多発したため「スラム街」と同じ意味で捉えられることも少なくないですが、実際には、日本の社会と経済の成長に不可欠な役割を果たしてきた重要な地域でもあります。
参考:日本にスラム街は存在する?「ドヤ街」と呼ばれる場所との違い
ドヤ街の語源とその由来
「ドヤ街」という言葉の響きには、独特の力強さがありますが、その語源については諸説あります。
一般的に知られている意味として、「宿(やど)」という言葉を逆さに読んだ「ドヤ」 という日雇い労働者のあいだで使われた逆読みの俗語が、いつしか地域全体を指す言葉として定着したのではないかと考えられています。
かつて宿泊所を指す業界用語(隠語)のようなもので、いわゆる「簡易宿泊所」を表現する言葉が語源となっているとされています[1]。
そして、この「ドヤ」が集まった場所――つまりドヤ街は、単に住まいを提供するだけではなく、独自の文化やコミュニティも形成していきました。それが後に、社会課題や支援活動とも密接に関わるようになっていくのです。
戦後の復興期と高度経済成長で生まれたドヤ街
戦後日本が焼け野原から立ち上がろうとしていた昭和20年代から30年代、都市には急速に労働力が必要とされていました。
特に、建設業や運送業など肉体労働を支える人手が求められ、全国から多くの男性が職を求めて上京しました。
彼らの多くは単身で、長期的な住居を持たず、その日暮らしのような生活を送っていたため、低価格で泊まれる簡易宿泊所が必要とされました。こうして自然発生的に形成されたのが、「ドヤ街」と呼ばれる地域です。
初めは一時的な滞在先だった場所が、いつしか長期的な住まいとなり、仕事場と住まいが密接につながる生活拠点へと変化していきます。
朝になれば「寄せ場」と呼ばれる場所に労働者が集まり、雇用主がその日必要な人数を選んで連れていくというスタイルが日常となっていました。
このようにしてドヤ街は、都市の成長を陰で支える労働者の町として、確かな存在感を持つようになっていったのです。
日本三大ドヤ街とは?
「ドヤ街」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどこに存在しているのかご存じない方も多いかもしれません。
日本にはかつて「三大ドヤ街」と呼ばれた全国から日雇い労働者が集まる場所がありました。
その地域とは、大阪の西成、東京の山谷、そして横浜の寿町で、それぞれの地域には異なる歴史と文化が今もなお根強く残っています。
ここでは、その三つのドヤ街の特徴や背景について、1つずつご紹介していきます。
大阪・西成(あいりん地区)
大阪市西成区に位置する「あいりん地区」は、かつて「釜ヶ崎」とも呼ばれており、日本最大のドヤ街として知られています。
現在も簡易宿泊所が数多く立ち並び、地域全体が独特の空気感を持っています。
高度経済成長期には、ここから多くの労働者が大阪の建設現場や工場へと送り出され、日本の経済を支える大きな労働力供給地となっていました。
朝になると「西成労働福祉センター」前に人が集まり、その日限りの仕事に出かける光景が見られたものです。
現在では、高齢化が進むと同時に、インバウンドの影響から外国人観光客向けの宿泊所の役割へと姿を変えつつあります。
東京・山谷
東京都台東区と荒川区にまたがる「山谷地区」も、日本を代表するドヤ街の一つです。
戦後の混乱期から昭和後期にかけて、多くの日雇い労働者がこの地域に集まり、次第に簡易宿泊所が密集するようになりました。
山谷もまた、都市のインフラ整備やビル建設といった高度経済成長の恩恵を受けた一方で、労働者たちは厳しい生活環境のなかで暮らしていました。日雇いの仕事は安定せず、病気やケガをしても十分な保障を得られないという現実がありました。
近年では、西成同様に一部がゲストハウスや簡易ホテルに改装され、外国人観光客の姿も見かけるようになっています。
また、定期的に開催される地域祭りや交流イベントなどを通じて、住民と外部の人々との関係づくりも進められています。かつての労働者の町が、少しずつ新しい形で再生されようとしているのです。
横浜・寿町
横浜市中区にある寿町も、港町として栄えた背景を持つドヤ街の一つです。特に港湾労働者や工場労働者を中心に発展し、1960年代から70年代にかけては非常に多くの人が暮らしていました。
この地域では、早くから生活困窮者への支援が行われてきました。寿町健康福祉交流センターをはじめとする公共施設の充実ぶりは、他のドヤ街には見られない特徴でもあります[2]。
また、寿町では地域再生のためにアートや演劇、写真などを通じた文化活動も行われており、かつてドヤ街だった街ならではの新たな意味を与えようという試みが見られます。
ドヤ街を通じて見える日本社会の課題と未来
ドヤ街は、日本の都市の片隅に静かに存在してきましたが、その中には今の社会が抱える本質的な課題がいくつも詰まっています。
目を凝らせば、そこに見えてくるのは経済的な不平等、支援の限界、そして人と人とのつながりの希薄さといった、現代社会が避けては通れない問題ばかりです。
かつて「働く男たちの街」と呼ばれたドヤ街も、時代の流れとともにその役割を変えてきましたが、その歩んできた歴史と現在から見えてくる2つの日本の社会課題があります。
経済的貧困と不安定な生活基盤
ドヤ街に暮らす多くの方々は、安定した職業や住まいを持たないまま、日々の生活をなんとかやりくりしておられます。その多くが日雇い労働や短期の仕事で生計を立ててきたため、経済的に常に不安定な状況に置かれていたのが現実です。
また、働ける年齢を過ぎたあとも、年金や退職金といった公的な備えが十分でないケースが多く、生活保護を頼らざるを得ない方も少なくありません。
生活の再建を試みたくても、そもそもスタート地点に立つための社会的な支援が行き届いていないという問題は、現在の日本でも大きな課題の1つとなっています。
高齢化と労働力の衰退
もう一つの深刻な課題が、高齢化の進行です。かつてはエネルギーに溢れていた日雇い労働者たちも、今では70代、80代という年齢になっています。
この高齢化問題は日本の核となりうる社会問題へと発展しています。
介護の必要性が高まる一方で、少子化による深刻な人手不足により、地域の医療や福祉体制は追いついていかなくなりました。
また、働き手の減少は労働力の衰退にもつながり、ドヤ街が急速に衰退していった時の状況が、現在日本全体で起こっていると言っても過言ではないのかもしれません。
ドヤ街を通じて考える、これからも住み続けられる日本であるために
ドヤ街の語源から始まり、その成り立ちや歴史、そして大阪・西成、東京・山谷、横浜・寿町という三大ドヤ街の特徴を通して見えてくるのは、決して一過性ではなかった、根深い日本の社会構造です。
経済的な貧困、高齢化、孤立といった課題は、ドヤ街だけに限らず、今の日本社会全体が直面している現実でもあります。
一方、近年では、かつてドヤ街と呼ばれた地域でNPO団体や住民の協力によって、 “貧困地域”から、“支え合いの文化が根づく場所”へと再評価されつつあります。
外国人観光客を受け入れる宿泊施設として生まれ変わるケースや、地域再生の拠点として注目される事例もそれらを象徴する1つの事例と言えるのではないでしょうか。
このように、ドヤ街を知ることは、私たちの社会における「格差」「支援」「老い」「働くことの価値」など、多くの問いを浮かび上がらせてくれます。決して過去の遺物ではなく、今この瞬間にも変化を続けている現場――それが、ドヤ街なのです。
これを機に、少しだけ視野を広げて、身近にある社会の課題について考えるきっかけになっていただければ幸いです。
お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
(KOBIT編集部:Fumi.T)
<参考文献>
[1]東京工芸大学,「横浜市寿地区ドヤ街の研究」,available at https://www.arch.t-kougei.ac.jp/yatsuo/assets/08kougai_miura_ohshima.pdf
[2] 公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会,available at https://www.yokohama-kotobuki.or.jp/
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND