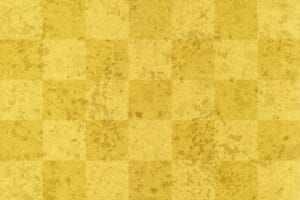おこめ券が440円分しか使えないのはなぜ?差額の理由を徹底解説!

お中元やお歳暮でいただく「おこめ券」。ふと額面を見たときに「500円と書いてあるのに、実際には440円分のお米しか交換できないの?」と疑問に思われたことはございませんか。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
本記事では、この“60円の差額”がどうして生じるのか、その理由をわかりやすくご説明いたします。あわせて、おこめ券を少しでもお得に使う方法もご紹介してまいります。
なぜおこめ券は440円分しか使えないのか?
おこめ券には「500円」と額面が印字されているにもかかわらず、実際にお米と交換できるのは「440円分」だけ。
そう聞くと「なぜ満額使えないの?」と不思議に思われるのも無理はありません。
この金額の差には、実は明確な理由がございます。おこめ券のようなギフト券は、ただ紙を発行しているだけではなく、さまざまな手間やコストが裏でかかっています。
そのため、発行価格と利用価値に差があるのは、おこめ券だけに限った話ではなく、ビール券や清酒券など他の商品券にも共通する仕組みとなっています。
では具体的に、その差額60円がどういった内容で構成されているのか、詳しく見ていきましょう。
差額60円の理由とその内訳
おこめ券の購入価格は1枚500円ですが、使用時に実際にお米と引き換えられるのは440円分まで。
この差額60円には、券の発行から流通、管理までを支えるためのコストが含まれています。
まず最も基本となるのが、券の印刷費です。
おこめ券は一般的な紙とは異なり、特殊な加工が施された偽造防止機能付きの用紙が使われています。この印刷や素材のコストは想像以上に高額になります。
また、全国各地のスーパーや米穀店におこめ券を流通させるためには、配送費用や取り扱い店舗への案内も必要になります。
さらに、利用後にお店から発行元に券を回収して精算するための管理費用も発生しています。
これら一連のコストをまかなうために、60円という差額が設定されているのです。
簡単に言えば、ギフト券という便利な仕組みを成り立たせるための「運営維持費」と考えるとわかりやすいかもしれません。
おこめ券の発行元の見解
おこめ券の発行元である全国米穀販売事業共済協同組合(通称:全米販)や、各地の農業協同組合(JA)では、この差額について「システムを安全かつ安定して運用するために必要な経費」と説明しています[1]。
おこめ券は全国の取扱店舗で共通して使える利便性があるため、そのぶん高い信頼性と管理体制が求められます。
特に、券の不正利用や偽造を防ぐためのセキュリティ対策にも相応の費用がかかっています。
また、使われた券を集計し、発行元が代金を店舗に支払うまでには精算業務という複雑な流れがあります。
これをスムーズに行うための事務作業やシステム維持費も、差額に含まれているのです。
つまり、この60円という金額には、ただの手数料ではなく、おこめ券の「信頼性」や「安全性」を保つための多層的なコストが含まれていると考えるべきでしょう。
使い方次第でお得になる?おこめ券の賢い利用法
おこめ券は贈答用として長年親しまれてきた商品券のひとつですが、実は使い方によって「お得」か「損」かが大きく分かれることもございます。
贈り物としていただく場合と、ご自身で購入して使う場合では、感じ方がまったく異なるため、それぞれのケースに分けて詳しくご紹介いたします。
ギフトとしての価値
おこめ券は、贈答用としての利用を前提に設計された商品券です。
そのため、もらった方にとっては「実質的な価値」が440円であっても、それほど気にならないのが実情ではないでしょうか。
贈り物というのは、金額そのものよりも「気持ち」が大切にされる場面が多くあります。
特に、お中元やお歳暮、内祝い、お悔やみ返しといった場面では、現金よりも柔らかい印象があるため、一定の品格と実用性を兼ね備えたおこめ券は重宝されてきました。
こうした点から見ても、おこめ券は「価格差を感じさせにくい」贈り物として、今も根強い人気を保っているのです。
自分用に買うとどうなる?
一方で、ご自身でおこめ券を購入して日常的に使おうと考える場合は、少し事情が異なります。
購入価格が500円に対して、交換できるのが440円分のお米となるため、実質的に60円の差額を負担していることになります。
この場合、「60円の手数料を払っている」と感じられる方もいらっしゃるでしょう。
そのため、普段のお買い物に使うというよりも、あくまでギフト用と考えるほうが、納得感が高いかもしれません。
他の商品券との比較で見る「440円」の意味
おこめ券のように、額面通りに使えない商品券は、決して珍しいものではございません。
たとえば「ビール券」や「清酒券」なども、券面の金額と引き換えられる商品の実際の価格に差がある場合があります。
お宝エイド参考記事:ビール券はどこで買える?近くのお店・買い方・注意点をご紹介
特に、全国で共通に使えるギフト券を運営するには、管理システムやセキュリティ対策にかかるコストが避けられません。
利用者が安心して使える環境を維持するためには、その維持費がどこかで必要になります。
そのコストを、利用者ではなく「贈る側」が負担するという仕組みは、ある意味とても合理的とも言えるでしょう。
贈答用の商品券においては、「信頼性」「利便性」「安心感」を維持するためのコストとして、この差額が存在しているのです。
つまり、「440円しか使えない」と感じるよりも、「60円で全国どこでも安心して使える仕組みを買っている」と捉えていただくと、納得感が少し変わってくるかもしれません。
「おこめ券が440円分しか使えないのはなぜ?差額の理由を徹底解説!」のまとめ
今回は、おこめ券の価格設定について、なぜ500円で購入した券が440円分しか使えないのか、その仕組みと背景をご紹介いたしました。
その差額60円には、券の印刷費や流通費、システム管理費など、目には見えない多くの運営コストが含まれております。
これは、おこめ券が安心・安全に流通し、全国の店舗で共通して使えるようにするために欠かせない費用です。
おこめ券に限らず、ギフト券にはそれぞれの事情と背景があります。
今回の内容が、少しでも皆さまの疑問解消や、今後の使い方の参考になれば幸いです。
本記事で紹介した「商品券」をはじめ、お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND