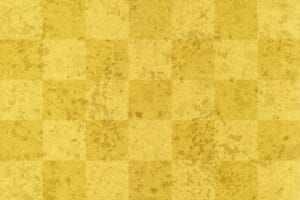コンビニに公衆電話はある?減りゆく設置台数の今とこれからの役割

かつては都市の交差点、学校の校門前、駅舎の中と、あらゆる場所に設置されていた公衆電話。しかしその数は年々減少の一途をたどっています。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
最大約93万台あった国内の公衆電話数は、2020年代には15万台前後にまで減っています。
本記事では、「コンビニと公衆電話」をテーマに、減りゆくある公衆電話の今とこれからの役割についてお伝えします。
公衆電話とコンビニの関係性の変化
1990年代末から加速度的に普及した携帯電話によって、2000年代初頭には多くの人が個人用携帯電話を持つようになり、次第に「外から電話をかけるための共用機器」としての役割が終焉を迎えることになります。
加えて、通信インフラの整備と通話料金の低廉化も公衆電話離れを加速させ、公衆電話は経済的にも維持が困難な存在となっていきました。
そのような中で、コンビニエンスストアという24時間アクセス可能な施設に公衆電話が併設される流れははじまりました。
セブンイレブンやファミリーマート、ローソンといった大手チェーンでは、利用者の利便性を考慮して店舗外壁などに公衆電話を設置してきたのです。
ただし近年では、設置スペースの有効活用や日々の業務負担軽減の観点から、公衆電話の撤去や新規設置の見送りが進められています。
スマートフォンの普及により、公衆電話利用頻度自体が大きく落ち込んでいるのは事実です。
とはいえ、災害発生時や一時的な携帯電話の故障など、想定外の状況に対応できる「保険的機能」としての価値は見過ごせません。
そのため、現在でも一部の店舗では現在も公衆電話が設置されているケースもあります。
参考:NTT東日本・西日本|公衆電話 設置場所検索[1][2]
公衆電話の撤去と維持のバランス:誰がどう決めているのか
公衆電話を残すか撤去するかの意思決定は、主にNTT東日本・NTT西日本が行います。
彼らは“ユニバーサルサービス制度”に基づき、一定数の公衆電話を維持する義務を負っています。
この制度は、通信手段が確保されていない地域や条件(病院や福祉施設周辺、防災拠点近辺など)に対して、最低限の通信インフラを提供する目的で存在します。
一方、設置場所の提供者であるコンビニ側にも判断権はあります。
たとえば、リニューアル工事でのスペース再編成、死角や治安上の問題、実際の利用頻度に応じて、継続設置が見直されることもあります。
また、公衆電話の筐体老朽化や修理・保守コストがかさむことも撤去の動機になりえます。
災害対策とコンビニの公衆電話の再評価
2011年の東日本大震災や2018年の北海道胆振東部地震など、近年発生した大規模災害は、再び公衆電話の価値を認識させる契機となりました。
災害時、携帯電話は回線のパンクや基地局の損傷により使えないことがある反面、公衆電話は通信回線の安定性・復旧性に優れ、優先接続が保証されるため、高い信頼性を誇ります。
このような特性を持つ公衆電話は、災害拠点となる公共施設や避難所、そして災害時に人が集まりやすいコンビニにこそ、引き続き必要とされています[3]。
住民の安心・安全を守る装置として、あらためて注目されているのです。
コンビニ側の思惑と新たな課題
コンビニ店舗で公衆電話を残す理由としては、防災インフラの一環としての社会的使命や、顧客満足度の向上といった目的が挙げられます。
また、高齢者や訪日外国人観光客への利便性として設置しているという店舗経営者の声もあります。
一方で、店舗敷地の有限性は無視できません。現在では荷物受け取り用ロッカー、ATM、EV充電スタンドなど、さまざまなサービス設備が求められる中で、全く収益を生まない公衆電話が優先順位を下げられてしまうのは避けられません。
また、公衆電話の管理・修理連絡の手間も店舗側の負担として残ります。
新しい公共インフラとしての可能性
注目されているのは、公衆電話が単独の通信手段としてだけでなく、他の公共設備と一体となる“多機能インフラ”として再活用できないかというアイデアです。たとえば、次のような試みが進められています:
- 災害時の非常電源供給機能付き公衆電話
- 無料Wi-Fiスポットのアンテナ拠点として利用
- 避難所案内や地域情報を発信するディスプレイ
こうした取り組みによって、公衆電話は過去の遺物どころか、次世代的な「スマート・公共サービス拠点」として存在価値を再構築可能です。
コンビニという“人が絶えず訪れる場”と、公衆電話の持つ“誰もが利用できる”という特性を掛け合わせることで、普段使いから非常時対応まで、幅広いニーズをカバーするインフラの一部となり得る未来が見えてきます。
「コンビニに公衆電話はある?減りゆく設置台数の今とこれからの役割」のまとめ
2040年までに現在の携帯通信インフラはさらなる発達を遂げ、IoTやAIによる“常時接続社会”が実現するとも言われています。
その中で公衆電話は、あくまで非常用・緊急用としての役割が中心となっていくでしょう。
しかし一方で、レトロブームや「日本ならではの風景」として公衆電話を好む外国人観光客も増えており、街なかのランドマークとして維持されるケースも見られます。
また、障がいや経済的理由により携帯電話を持てない層にとっては、今後も変わらぬ“通信の最後の砦”であり続けると考えられます。
コンビニという現代のライフライン的存在に助けられながら、公衆電話はこれからもしばらく、確かな役割を果たし続けていくのではないでしょうか。
お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
<参考文献>
[1]NTT東日本,「公衆電話 設置場所検索 」,available at https://publictelephone.ntt-east.co.jp/ptd/map/
[2]NTT西日本,「公衆電話 設置場所検索」,available at https://www.ntt-west.co.jp/ptd/map/
[3]公益財団法人 日本公衆電話会,「セブンイレブン店舗に設置している災害時用公衆電話(特設公衆電話)の点検サポート活動」,available at https://www.pcom.or.jp/topics/ntt/tky2022-029.html
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND