児童労働・教育機会の問題はじめ、すべての社会課題を身近に。『路傍の石』を今こそ読む

名著で実感する「支援」の力、必要性、難しさ
世界に残る児童労働の問題や、教育機会の均等の問題に関心をもち、それらの問題解決の一助となる個人としての支援(寄付など)に関心を持ったとき、いざ行動を起こす段になって「踏ん切りがつかない」ということは、支援を志したことのある多くの方に経験のあることだと思います。
そうした際に、「支援」を行動に移せる方にはどんな特徴があるのでしょうか。さまざまな答えはあろうかと思いますが、一つには「支援の先にいる人間に対し、深い理解と感受性を持っている」ということのように思います。
そうした素質は、決して先天的にだけ備わるものではなく、さまざまな行動によって育まれるはずです。たとえば、人は小説を読むことを通じて、他者の痛みや境遇が実感をもって理解できるという瞬間があります。そうした擬似体験を通じ、「一歩踏み出す」力が手に入ることもあるのではないでしょうか。
本記事では「支援」にまつわる小説として、1937年に出版された山本有三著・『路傍の石』を解釈し、ご紹介したいと思います。
『路傍の石』の教え – 支援には、経済の壁と、文化や思想の壁がある
『路傍の石』の時代背景は明治時代の半ばにある日本で、吾一という高等小学の2年(いまでいう小学6年生)の少年が主人公です。この吾一という少年を取り巻く「支援」の物語が本著の序盤の大部分を占めますので、まずは本著のいくつかの台詞を通じて、吾一の人間性や境遇をいくらか感じていただければと思います。
「そのころ、吾一はおやつをたべていなかったから、わけても腹がすいていた。お小づかいをもらわないわけではないけれども、小づかいは、毎日、貯金バコにほうりこむことにしていた。買い食いをしないで、小づかいはなるたけ貯金するようにと、学校で先生から言われて以来、それを実行しているのである。」
「貯金なんて腹がへってやりきれないから、やめてしまおうかと思ったが、先生に言われたことが守れないのはくやしいと思った。ところが、ほかの友だちに聞いてみると、友だちもみんなやめてしまったという。『それじゃおれも……』と、ひょいと、よわ気になりかけたが、彼はこういう時、かえって、えこじになる子どもだった。」
「彼は、毎日、歯をくいしばって、おやつの時間を辛抱した。(中略)ある時なんか、たまらなくなって、貯金バコに手をかけたこともあったが、おっかさんからあけ方をおそわっていないものだから、どうしても、あかなかった。あけられないのは、くやしかったが、あとでは、それをしあわせだと思った。」
(上記『くち絵のかわりに』より)
吾一の健気で実直なところが、伝わってくれるのではないかと思います。
吾一は勉学優秀な少年でした。しかし裕福でない家庭の事情から、中学校で学ぶことをあきらめなければならないかもしれない岐路に立たされることになります(※ 当時、中学校進学は義務ではなく、志望者が進学するものでした)。
「中学にはいって、それからだんだん上へのしていくか、それとも、このちいさな町の土になってしまうか、ここが一生のわかれ道だった。吾一はかねてから、はいりたくってたまらなかった。先生も、おまえは、はいるほうがいい、と言ってくれた。だが、彼はすぐ手をあげて、『先生、はいりたいんです。』と、言えるような、めぐまれた境遇にいるのではなかった。」
(『中学志望』より)
先に述べたように、『路傍の石』の序盤は、こうした境遇におかれた吾一への「支援」の物語です。
はじめに吾一の「中学に入りたい」という意志に気づき、行動したのは、吾一の担任である次野先生という人物でした。次野先生は、自身の友人であり、吾一を小さいときからかわいがってきた隣人でもある書店・稲葉屋の店主、安吉に学資の支援をたのみこみます。
「裏の子どものことなんだけれど、君もあの子をかわいがっているようだが、どうだろう、あの子に学資を出してもらえないかね。(中略)安さん、ぼくはああいう子どもを、中学に入れてやりたいのだ。あれは見どころのある子どもだよ。」
(『実学』より)
このように頼まれた安吉は、次のように返答します。
「そりゃ、わたしも考えないことじゃないが、しかし、そいつはどうかな。(中略)なかなか、そう簡単にはいかないと思うのだ。(中略)あの子のおとっつぁんは、士族だからね。」
学資の支援について「考えないことじゃない」と考える隣人がいたことは、吾一の器量ゆえであり、純粋な「幸運」でもあったと言えそうです。
はじめは吾一への支援に難色を示した安吉ですが、(物語の上でもいくつかの『事件』があり…)ぜひ吾一に学資の援助をしたいと、やがて心変わりをします。ここまでであれば「支援の成就」という話になるはずだったのですが、支援についての話がまとまりかけたところで、吾一の父である庄吾が、支援の段取りのすべてを覆す発言をします。
「おまえ、中学へ行きたいんだそうだな。(中略)しかし、おとっつぁんが、いけないって言ったら、どうする。」
この衝撃的な言葉から、庄吾は、旗本(当時の武士の階級)の出身で、のちに学者となった新井白石(あらい・はくせき)について滔々と述べます。
「白石は(中略)よく勉強した。しかし、それだけではない。白石には気概があったのだ。武士としての気概があったのだ。(中略)河村瑞賢(中略)が白石を見込んで(中略)学問研究のために、三千両で買った家やしきを付けて、さしあげましょうと言ってきた。(中略)ところが、白石は、(中略)『ご厚意はかたじけのうございますが。』と言って、ポーンと、はねつけてしまったのだ。(中略)どうだい、胸のすくような、いい話じゃないか」
「親切らしいことを言ってくるやつは、きまって腹の中にたくらみを持っているのだ。おとっつぁんはな、そのたくらみに引っかかって、どれだけ、ひどい目にあったかしれやしねえ。おれのうちがこんなになったのも、おとっつぁんが人がよかったから、いけなかったんだが、第一は世の中が悪くなったからだ。(中略)吾一、人を信じちゃだめだ。うまい話に乗っかっちゃだめだぞ。(中略)親切の底には、きっと、なんかがあるんだ。」
(『先祖と家がら』より)
そのような庄吾の強い反対から、吾一への「支援」は結局、跳ね除けられてしまいます。これが本書におけるはじめの「支援」の物語の顛末であり、吾一は結局、中学校へは入れず、伊勢屋という呉服屋に奉公に出ることとなります。そこからの物語は、ぜひ本著の原文を読む楽しみとしていただければと思います。
この一連の物語からの教訓は2つ、あると考えます。一つは、経済的問題で学びをあきらめなければならない子供が当時の日本におり、また現代の世界にもいるという事実です。そしてもう一つは、たとえ経済の壁を乗り越えたとしても、次には文化や思想の壁が立ちはだかるということだと考えます。
『路傍の石』は、吾一から「学び」を奪ったとも言える庄吾に対しても、たんなる「悪者」で終わらせていません。すなわち、幕末の生まれである庄吾についてもまた「子ども時代」が描かれ、その価値観がどのように形成されたか、説得力をもって語られています。幕末の慶応の時代に士族の子として生きた庄吾が、「世をのろい、人を信じなかった」人間にどのようにしてなったのか、その点も併せて読むことで、「支援の難しさ」がいっそう理解されるように思います。
現代の「吾一」は日本におり、そして海外にいる。支援の手立てとは
ここまで紹介したような『路傍の石』の内容は「過去の話」なのでしょうか? ある面ではそう、と言えるかもしれません。
しかし私には、ここでハンス・ロスリングという公衆衛生学者のプレゼンテーションが思い起こされます。ハンスは『FACTFLLNESS』というベストセラーの著者としても知られており、「データに基づく世界の見方」を提唱している人物です。
「社会と文化は岩のように動かないものではない。社会も文化も変わっていく」 [3] という信念を持ち、それを一人あたりGDPという指標を手段に解き明かす、明快な論調で記した書籍『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』は、日本でもベストセラーとなりました。
ハンスは一人あたりGDPの数値を見ると、社会や文化のあり方を大まかに推定できるという自説を持ち、それを体感できるWEBサイトも立ち上げています。この考え方を元にすれば、『路傍の石』が出版された当時の1937年の日本は、現在でいうどの国と状況が似ているのかを推測することもできます。
『路傍の石』執筆当時の日本と、いま経済状況が似ている国は…
実際に当時の日本の経済水準を調べ、それを現代の諸外国と比べてみましょう。『路傍の石』出版直前の1935年には一人あたりGDPは2,406ドルでした [1], [2] 。現在、これと近い経済水準の国の一例として、ネパール(1人あたりGDPが2,613円)やジンバブエ(1人あたりGDPが2,568円)があります [3] ※。
ハンスの主張を信じるならば、「『路傍の石』で描かれる日本はいまの日本と違うようにも見えるが、それはハンスの言うように『社会も文化も変わった』結果であり、かつて(1937年)はまるで環境が違ったからだ」ということになります。山本有三が生きた、まさにその「別の国」であったかのような時代が『路傍の石』では描かれていることになります。そして、吾一が体験したその時代の現実の多くはいま、むしろネパールやジンバブエといった諸外国にこそ残っているのではないか、とも推測できます。
この考えをもう一つ推し進めると、「吾一」のような個人はいまやネパールやジンバブエにこそ生きているのかもしれません。そしてこれらの国に支援をすることは、時を超えて「吾一に接触する」ことになるのではないか、とも思われてきます。
※ [1] [2]からは1990年国際ドル基準の数値、[3] からは2011年国際ドル基準の数値を引用しているため、比較はあくまで参考値です。
いま私たちには、個人として支援の決意をし、支援先を選ぶことができる
『路傍の石』のような日本生まれの小説には、日本人の名前をもって生まれた人物がいて、日本の歴史と地理に基づいたストーリーが描かれることから、日本人にとりわけ強く訴える力があります。(その実際の「訴える力」については、ぜひ実際に本著を読み、確かめていただきたいと思います。)
もしも「吾一」の苦境への共感を覚えたならば、それをたんなる感傷で終わることもできますが、実際に行動に移すこともできます。すなわち、稲葉屋の安吉がしたような「支援」という行動です。
『路傍の石』で描かれた「支援」は、士族であった吾一の父・庄吾の強い反対に遭い、実を結ぶことがありませんでした。こうした状況に「もしも」があるのかは分かりませんが、いまでは国際人権基準の一つとして「子どもの権利条約」が1989年に国連で採択されており、「教育の権利」をいかに守るかについては特に専心して制定されています。こうした権利の保護について活動する団体を支援すれば、間接的にでも「吾一を助ける」ことが叶う可能性はあるでしょう。
『路傍の石』において存在した、愛川吾一(中学校に進学したい子ども)、愛川庄吾(それに反対する父親)、そして次野先生と安吉(学資の支援を申し出た支援者)という三者のほかに、もしも「人権団体」が物語の舞台に存在していたならば、吾一が奉公に出る本著の中盤以降は、また違った展開になったのではないか…。
そんな想像を膨らませて支援をするならば、現代に生きる私たちの「支援」もきっと、また違った重みを持つのではないか、そんな風に思われます。
本記事で紹介した書籍
- 路傍の石 (新潮文庫)
新潮文庫から文庫化されており、紙の本はもちろん、スマホやタブレットで読めるKindle版もあります。 支援に関心のある方も、本記事を読んで関心を寄せてくださった方もぜひ、ご一読ください。 - 「FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」(日経BP)
ジャンルは異なる実用書ですが、「支援」の実感を持てる本、世界のつながりを感じる本という意味で、『路傍の石』と支援の副読書として紹介させていただきました。
『路傍の石』で描かれたような「子供が教育を受ける権利」「児童労働から保護される権利」については、今では国際人権基準にうたわれています。
「こうした人権基準を享受でき、人間らしく生きることのできる世界の実現」をめざすNPOは数あります。一例を挙げれば、「公益社団法人アムネスティ・インターナショナル」「認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン」などです。「お宝エイド」では物品の寄付を通じて、これらNPOの活動を支援することができます。
参考文献
[1] 斎藤修,「世界史における日本の近世: 長期の視点からみた成長・格差・国家」,日本學士院紀要 (72) ,pp. 233-250,2018.
[2] 攝津斉彦・J.-P. バッシーノ・深尾京司,「明治期経済成長の再検討:産業構造 , 労働生産性と地域間格差」,『経済研究』第67巻,pp. 193-214,2016.
[3] 経済に関するデータ,世界統計, available at https://www.worldbank.org
[4] 子どもの権利条約 _ ユニセフについて _ 日本ユニセフ協会 available at https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
KOBIT編集部:滝田 潤 KOBIT公式サイト
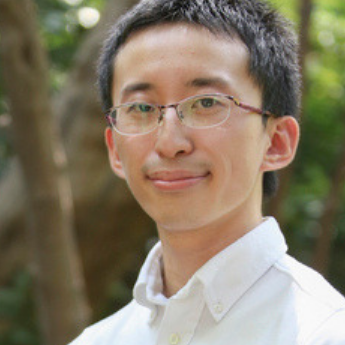
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND




