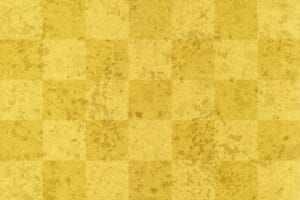公衆電話とテレホンカードの使い方と活用法|災害時の備えにもなる最後の通信手段

最近、ニュースや防災番組などで「災害時や緊急時には公衆電話が頼りになる」と聞いて、ふと気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
携帯電話が普及して久しく、公衆電話を使う機会がめっきり減った今、いざという時の使い方を覚えておくことはとても大切です。
昔は当たり前だったテレホンカードも、今ではすっかり見かけなくなりましたが、実は現在でも公衆電話では利用可能です。
この記事では、公衆電話とテレホンカードの使い方や通話料金、防災に役立つ情報まで、やさしく丁寧に解説いたします。
公衆電話とテレホンカードの使い方
公衆電話の操作は、基本的には昔とあまり変わっていません。
とはいえ、使い慣れていないと戸惑うこともあるかもしれませんので、あらためて手順を確認しておきましょう。
一般的な公衆電話では、受話器を取ってからお金かテレホンカードを入れて、発信音が聞こえてから電話番号を押すという流れになります。
使用できる硬貨は、主に10円玉と100円玉です。ただし100円玉を使った場合、通話が途中で終わるとおつりは出ませんので、その点にはご注意ください[1]。
おつりを気にせず使いたい場合は、10円玉のほうが安心です。
テレホンカードを使用する場合は、カード差込口にまっすぐ差し込むだけでOKです。
カードの種類には50度数(500円分)や105度数(1,000円分)などがありますが、どちらも現在でも一部の電話機では問題なく使用できます。
カードを使うと、残りの度数が表示されるため、通話時間の目安にもなって便利です。
使い終わったら、カードは自動的に戻ってくるか、そのまま挿入口に残りますので取り忘れのないようにしましょう。
なお、最近の公衆電話には「緊急通報ボタン」が備え付けられている機種も増えています。
このボタンを使うと、硬貨やカードがなくても、110番や119番、118番といった緊急通報が無料で発信できるようになっています。
公衆電話の通話料金の目安
公衆電話を利用する際に気になるのが「どれくらい話せるのか」という点ではないでしょうか。携帯電話とは異なり、公衆電話は通話相手の種類や時間帯によって料金体系が変わる場合があります。
ここでは、2025年現在の公衆電話における通話料金の目安を、固定電話と携帯電話に分けてご案内いたします[2]。
固定電話への通話は距離に関わらず一律料金
固定電話への通話では、国内であればかける相手の距離に関わらず、1回の料金で話せる時間は一律10円で56秒通話できます。
ただし、海外への国際通話は国や地域別によって通話料金が異なりますので注意が必要です。
携帯電話への通話は固定電話より高い
一方で、携帯電話への通話に関しても距離や時間帯による料金の変化はありません。
10円でおおよそ15.5秒通話できる設定になっています。
現代では家族や知人が携帯電話しか持っていないということも多いため、公衆電話から携帯電話にかける機会も多くなってくるかもしれません。
固定電話より高い料金設定となっていますので、限られた通話時間のなかで用件を伝えるには、あらかじめ伝えたい内容を明確にしておくことがポイントになります。
とくに緊急時などは、手短かに要点だけを話すよう意識しておくと良いでしょう。
災害時、公衆電話が「最後の通信手段」になる理由
地震や台風といった自然災害が発生した際、携帯電話やインターネットがつながりにくくなることがあります。
多くの人が一斉に連絡を取ろうとするため、回線が混雑し、つながるまでに時間がかかったり、まったく通話できなかったりするケースも少なくありません。
そうした状況でも、公衆電話は非常に高い信頼性を持っています。
日頃は使う機会が少ないかもしれませんが、いざというときに本当に頼れる手段として、公衆電話の役割が再認識されているのです。
通信制限なし・無料開放されるケース
災害発生時には、通信会社が携帯電話の利用に制限をかけることがあります。これは回線の混雑を緩和し、救急や警察などの緊急連絡を優先的につなげるための措置です。そのため、個人のスマートフォンではなかなか連絡が取れないという状況に陥る可能性があります。
一方で、公衆電話はこのような通信制限の対象外とされており、非常時でも比較的つながりやすいという特徴があります。
また、NTTが災害救助法の適用を受けた地域に対しては、公衆電話の通話料金を一時的に無料にする措置を取ることもあります[3]。
このように、公衆電話は「制限を受けにくい」「無料になる場合がある」という点で、災害時において大きな利点があるのです。
停電時も利用可能な公衆電話の強み
災害時には停電も起こりやすくなります。電気が止まってしまうと、スマートフォンの充電もままならず、連絡手段が限られてしまうことになります。
しかし、公衆電話の多くは非常用電源やバッテリーを備えており、停電中でも使用できる設計になっています[4]。
ただし、テレホンカードは通電を必要とするため、停電時には使えないことがあります。そのため、停電下で公衆電話を利用する場合は、硬貨(とくに10円玉)を用意しておくと安心です。
また、受話器を取ってすぐに「ツー」という発信音が確認できれば、停電時でも正常に通話が可能な状態と判断できます。
このような仕様は、万が一のときに確実な通信を確保するために非常に重要なポイントとなります。
家庭で準備しておきたい3つのもの
いざというときに公衆電話を活用するためには、日頃からいくつかの備えをしておくことが大切です。
まず1つ目は、停電時に備えて10円玉を数枚常備しておくこと。
小銭入れや防災袋に入れておくと、咄嗟の時にもすぐ使えて便利です。
2つ目はテレホンカードです。
平常時であれば便利に使えますし、財布に1枚入れておけば外出先で公衆電話を使いたくなったときに役立ちます。
現時点でも一部の電話機では、問題なく使用可能です。
そして3つ目は、公衆電話の設置場所を事前に確認しておくことです。
災害が起きてからでは焦ってしまい、探すのが困難になります。
ご自宅や職場、よく行く場所の周辺にどこに公衆電話があるのか、家族と一緒に調べておくとより安心です。
公衆電話はどこにある?見つけやすい設置場所一覧
普段の生活で公衆電話を見かける機会は少なくなりましたが、実際にはまだ多くの場所に設置されています。
特に、災害時や緊急時に備えて、公衆電話の設置は法律で最低限の数が維持されており、全国で約14万台以上が稼働しています。
とはいえ、その場所を把握していなければ、いざというときに探し回ることになりかねません。
あらかじめ「どこに行けば見つかりやすいのか」を知っておくことは、安心・安全な備えのひとつです。
駅・病院・学校など、設置されやすい場所とは
現在、公衆電話が比較的見つけやすい場所には一定の傾向があります。
まず代表的なのは駅構内や駅前です。通勤・通学や観光の際に多くの人が利用するため、駅周辺には1台以上設置されていることが多く、屋外タイプや構内の目立つ場所に置かれています。
また、病院内やその出入口付近も設置率が高い場所です。携帯電話の使用が制限される場面でも、公衆電話なら問題なく使えるため、今でもニーズが根強く残っています。
さらに、中学校や高校といった教育機関、市役所や図書館などの公共施設、大型ショッピングセンターや高速道路のサービスエリアなども要チェックポイントです。
特に子どもや高齢者が利用する施設には、公衆電話が意識的に設置されている傾向があります。
身近な場所を事前に把握しておく重要性
災害や緊急時に冷静な判断を下すのは、決して簡単なことではありません。
そんなときに、公衆電話の設置場所をすでに把握していれば、焦ることなくすぐに行動に移すことができます。
現在では、NTT東日本・西日本の公式サイトで、住所や駅名などを使って最寄りの公衆電話を検索できるサービスが提供されています[5][6]。
ご自宅の周辺や、通勤・通学経路、よく行く商業施設などについて、一度は調べておくことをおすすめします。
特に高齢のご家族がいらっしゃる場合は、家族全員で情報を共有しておくと、より安心感が得られるのではないでしょうか。
「公衆電話とテレホンカードの使い方と活用法|災害時の備えにもなる最後の通信手段」のまとめ
携帯電話が当たり前になった現代において、公衆電話の存在はつい忘れられがちです。
しかし、災害時や停電のときには、通信制限を受けず、電源がなくても使える「最後の通信手段」として、非常に大きな役割を果たします。
今後の災害に備えて、ご自宅や職場、通学・通勤ルートの周辺にある公衆電話の位置を確認しておくことは、とても有意義な防災行動です。
また、10円玉やテレホンカードを常備しておくことで、いざというときに落ち着いて連絡が取れる環境を整えておけます。
何気ない日常のなかにも、いざというときの備えはとても大切でので、この機会にご家族と一緒に、公衆電話の大切さを共有してみてください。
もしこの記事が「もう一度公衆電話について思い出す」きっかけになりましたら幸いです。
本記事で紹介した「テレホンカード」をはじめ、お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
<参考文献>
[1]NTT西日本,「公衆電話の種類と使用方法について
」,available at https://www.ntt-west.co.jp/info/support/teiden.pdf
[2]NTT東日本,「公衆電話料金」,available at https://www.ntt-east.co.jp/ptd/contents/mag_public_charge.html
[3]NTT東日本,「災害時の通信手段について」,available at https://www.ntt-east.co.jp/info-st/saigai/index.html#gaitou
[4]NTT西日本,「よくあるお問い合わせ|停電時でも公衆電話は使えるの?」,available at https://www.ntt-west.co.jp/ptd/inqury/q_and_a.html#q2
[5]NTT東日本,「公衆電話 設置場所検索 」,available at https://publictelephone.ntt-east.co.jp/ptd/map/
[6]NTT西日本,「公衆電話 設置場所検索」,available at https://www.ntt-west.co.jp/ptd/map/
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND