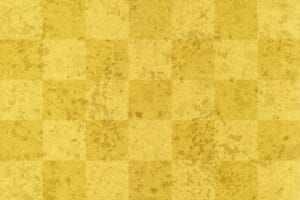田崎広助とは?朱富士(赤富士)や阿蘇山など山に魅入られた生涯と作品価値

実家の断捨離やパートナーの遺品整理をしているとき、額縁に収められた一枚の絵が目に留まり、署名を見ると「田崎広助」とあり、価値のあるものかもしれないと思い、気になって調べ始める方も少なくありません。
お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。この機会にお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
田崎広助は、日本の山々を生涯描き続けた洋画家であり、朱色に染まる富士山「朱富士」や阿蘇山の作品で広く知られています。
この記事では、田崎広助の生い立ちから生涯を紐解きながら、彼が作り上げた代表作とその作品価値に迫ります。
田崎広助とは?日本を代表する山岳画家の生涯を紐解く
田崎広助とは、どのような画家だったのか。ここでは彼の生涯を遡りながら、日本美術界で確固たる地位を築いた画家「田崎広助」をご紹介していきます。
八女での生い立ちと学生時代
田崎広助は1898年(明治31年)に福岡県八女郡北山村(現在の八女市立花町)で生まれ、本名を田﨑廣次といいました。
3歳の頃に母親の嫁入り道具である銅たんすに金火箸で模様を刻んだことが、彼の絵心が芽生えるきっかけだったと言います。
後にこの行為を本人は「自分の処女作」と語ったほど、早くから芸術への関心を強く持っていたことが伺い知れます。
やがて福岡県立八女中学校に進学した、自宅から片道8キロの道のりを徒歩で通ったといわれています。
雨の日には裸足で走り抜けることもあったそうで、この経験が後に山岳を題材にした画家としての体力培ったとされています。
自然と共に過ごした八女での日々は、田崎広助の作品世界に深く根付く土壌となったといえるでしょう。
師範学校から画家への転身
田崎広助は八女中学を卒業後、東京美術学校進学を希望していましたが、父親の反対受け、教員になることを強いられて福岡県師範学校へ進学しました。
卒業後は小学校で図画の教師を務めながら、独学で絵画の勉強に勤しむようになります。やがて絵画への情熱を捨てきれなかった田崎は、1920年に家族の反対を押し切って上京を決意します。
このとき図画の教員としての転機とも重なり、それを断ったことで父親からは勘当されるほどでしたが、それだけ強い覚悟をもって画家の道に進んだのです。
教師という安定した職を離れても、絵を描くことこそが自分の使命だと信じ、上京後は多くの指導者や仲間との出会いを通して技術を磨いていきました。
この勇気ある選択が、後の輝かしい画業の第一歩となったのです。
安井曾太郎に師事から始まった修業時代
1920年(大正9年)に上京した田崎広助は、本郷の駒本小学校の図画教師として働きながら、安井曾太郎に師事して二科会に所属します。
「日本のセザンヌ」とも呼ばれる存在であった安井曾太郎のもとで、描写力と構成力を徹底的に鍛えられました。
安井の洗練された構成力と色彩の扱いは、田崎広助の作風に深く反映されていきます。
その後1923年に発生した関東大震災で被災した彼は京都に移住することになります。
ここで同僚の教師だった女性と出会い、後に結婚。生活を安定させながらも、本格的に画業へと専念するようになります。
この京都時代は、精神的にも芸術的にも田崎にとって転機となった時期です。
フランス留学と国際的画家としての開花
田崎広助の才能が国内で認められ始めたのは、1926年(昭和元年)に第13回二科展で初入選した頃からです。
この受賞を機に、さらに高みを目指して1932年(昭和7年)にはフランス・パリに渡ります。当時、海外に留学する日本人画家はまだ少なく、田崎にとっても大きな挑戦でした。
フランスではサロン・ドートンヌ(秋の展覧会)に出品し、1933年(昭和8年)に見事入賞。日本人としては異例の快挙であり、フランス国内の新聞でも大きく取り上げられました。
これは、彼が無名の存在から国際的な画家として認められる一歩となった象徴的な出来事です。
パリでの2年間の滞在を通じて、田崎は西洋の伝統的な技法や色彩理論を吸収しながらも、自分ならではの「東洋的視点」を融合させた作風を模索していきました。
この時期に得た経験は、後の山岳画シリーズにも大きな影響を与えることになります。
山岳画家としての確立と日本美術会発展への貢献
1935年(昭和10年)頃に日本へ帰国した田崎は、一水会の創立に参加し、以後の日本美術界において重責を担う存在となっていきます。
戦後は美術展の審査員や評議員としても活躍し、多くの若手画家の育成にも貢献していきます。
同時期に日本の山々に魅了された田崎は「山岳画家」として確立をしていきます。
彼の代表作である「朱富士」シリーズが描かれるのはこの時期であり、雄大な富士山を朱色で染め上げた構図は、多くの人々の心に強く残る名作として現在でも人気があります。
富士山のほか、阿蘇山・桜島・浅間山といった各地の山々を題材にしながらも、単なる風景画にとどまらず「山の魂」を描き出すことに田崎は注力しました。
1975年(昭和50年)には文化勲章を受章し、日本美術の発展に対する長年の功績が公式に認められました。
1984年に86歳で亡くなるまで、田崎広助は絵筆を取り続け、山岳画の第一人者としてその地位を揺るぎないものにしていきました。
田崎広助の代表作と買取価値
田崎広助は生涯にわたり、日本の山々を題材にした雄大な作品を数多く残しました。
なかでも富士山を朱色に染めた「朱富士(赤富士)」シリーズは特に有名で、彼の画業を象徴する作品として高く評価されています。
さらに阿蘇山や桜島、浅間山など、自然の壮大さを表現した山岳画は今も多くの人々を魅了し続けています。
こうした作品は、西洋の油彩技法を用いながらも日本画の要素を取り入れた独自の構図や色彩感覚が特徴的です。
輪郭線を明確にしつつ平面的に構成された描写は、山と対峙するような迫力を観る者に与えます。
こうした彼の作品は国内外のコレクターに人気が高く、リトグラフや水彩画でも数万円、油彩画になると数十万円の価値で取引されることも珍しくありません。
2017年(平成28年)には、田崎広助の生まれ故郷である福岡県八女市に田崎廣助美術館[1]が開館し、死後40年以上経った現在も、彼の遺した作品の数々に多くの人が魅了され続けています。
お役目を終えた絵画をお持ちなら。支援寄付という新たな価値を
絵画の価値は作家の人生の足跡とともに残り続け、時の経過とともに上がっていくものです。
しかしながら、絵画の価値は残り続けても、あなたにとっては年を重ねるとともにお役目を果たすタイミングも少なからずやってくることでしょう。
もし、そうした絵画を遺品整理や断捨離を機に手放すのであれば、価値を必要としている方にぜひつなげて頂ければと思います。
お譲りできるご家族やご友人へ、あるいは買取を通じて新たな方の元へなど、価値のつなげ方は色々とありますが、お宝エイドでは、支援寄付という新たな価値を生み出す活動を行っています。
あなたがこれまで手にしてきた絵画を通じて、この機会に社会貢献へとつなげてみませんか。
本記事で紹介した「田崎広助」をはじめ、お宝エイドでは様々な物品を通じたNPO団体の支援を行うことが出来ます。お宝エイドでは郵送いただいた「お宝」を換金し、ご指定いただいたNPO団体の活動原資として送り届けます。あなたもお宝エイドでの支援活動をはじめてみませんか。
(KOBIT編集部:Fumi.T)
<参考文献>
[1] 八女市,「田崎廣助美術館」,available at https://www.city.yame.fukuoka.jp/art_museum/index.html
あわせて読みたいおすすめ記事
RECOMMEND